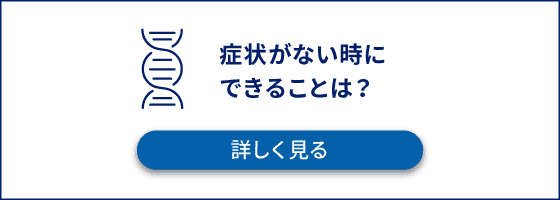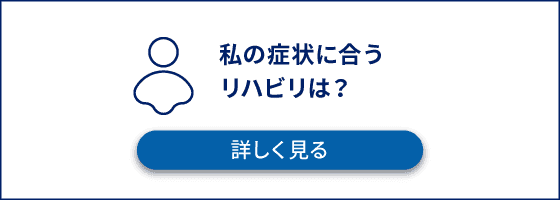3つの治療のポイント

進行・悪化を抑えるために、知っておきたいことは?
【治療のポイント1】
早いうちから多発性硬化症(MS) の治療を始め、それを続けることで、多くの患者さんは障害の進行・悪化を抑えることが期待できます。
【治療のポイント2】
MSの疾患活動性が高い場合は、最初の治療から高い有効性が報告されている薬剤を用いて、障害の進行・悪化を抑える治療が考慮されることがあります。
【治療のポイント3】
できる限り「あなたらしい生活」を続けるために、また、「やりたい」と思ったことを実現できるようにするために、主治医との「相談」は重要です。
【治療のポイント1】
早いうちからMSの治療を始め、それを続けることで、多くの患者さんは障害の進行・悪化を抑えることが期待できます。
多発性硬化症(MS)を治療する理由

MSは、治療をしないとどうなるの?
多発性硬化症(MS)は治療せずに放っておくと、脳の容積が減少(脳萎縮)し、脳萎縮の進行とともに、認知機能障害(集中力・理解力・記憶力の低下など)が現れることも少なくありません。
MSは多くの場合、「再発(症状が出る)」と「寛解(症状が治まる)」を繰り返します。しかし、症状が治まっている寛解期であっても、MSが治ったわけではなく、水面下ではミエリンの障害(脱髄)や神経細胞自体の障害(変性)が持続しているといわれています。
そのため、MSを治療せずに放っておくと、体の機能の障害が徐々に進行してしまうことも少なくありません。
MSによる障害の進行[イメージ図]


障害の進行って、抑えられるの?
MSは多くの場合、「再発(症状が出る)」と「寛解(症状が治まる)」を繰り返します。そのため、再発を抑える治療をせずに放っておくと、体の機能障害が進行・悪化してしまうことも少なくありません。
しかし、“早いうち”からMSの治療を始め、それを継続して行うことで、障害の進行を抑えることが期待できます。今は、そのための薬物治療があります。
再発を抑える治療をしない場合
[イメージ図]

再発を抑える治療を始めた場合
[イメージ図]

早いうちから再発を抑える治療を始めた場合 [イメージ図]

再発寛解型から、再発がなくても体の機能の障害が徐々に進行していく「二次性進行型」(SPMS)に移行したとしても、今度はSPMSに対する治療を早いうちから始め、それを続けることが重要です。
「再発寛解型」および「二次性進行型(SPMS)」については、こちらを参照
【治療のポイント2】
MSの疾患活動性が高い場合は、最初の治療から高い有効性が報告されている薬剤を用いて、障害の進行・悪化を抑える治療が考慮されることがあります。
この治療には、飲み薬(カプセル、錠剤)や注射剤(ペン型、シリンジなど)、点滴剤を使います。どちらの薬剤がよいかは、患者さんの状態によって異なりますから、投与回数や剤形も含め、主治医の先生と相談しながら決めるとよいでしょう。
寛解期の治療を始める時、長期的な安全性・有効性を考えて、ベースライン薬と呼ばれる薬剤で治療することが多いです。
しかし、早期からMSの疾患活動性が高い時は、最初の治療から高い有効性が報告されているMSの薬剤での治療が考慮されることがあります(early intensive therapyといいます)。


MSの症状が残っている時は、どんな治療をするの?[2]
患者さんによっては、MSの症状が出ている再発期が終わって寛解期になっても、感覚の異常や痛み、脱力、うつなどの症状が、完全には治まらずに残ってしまう場合があります。このような症状を和らげるために、それぞれの症状に応じた薬剤などを使います。

症状が初めて急に出た/再発した時はどんな治療をするの?[1]
MSの症状が急に出た初発時や再発した時を「急性期」と呼びます[2]。
急性期には、ミエリンで起こっている炎症をしずめ、症状を速やかに抑えることが大切です。
急性期には、ステロイド剤を点滴注射する「ステロイドパルス療法」が主に行われます。それでも効果がみられない場合は、「血漿浄化療法」が行われることもあります。

【治療のポイント3】
できる限り「あなたらしい生活」を続けるために、また、「やりたい」と思ったことを実現できるようにするために、主治医との「相談」は重要です。
多発性硬化症(MS)の治療で大切なのは「相談」
医師・看護師に相談してもいいの?[2]
MSの治療は長期にわたります。そうなると、医師との関係が大切になります。
お互い人間ですから、ウマが合う、合わないがあるのも事実です。それでも、医師は患者さんのためになる多くの情報を持ち合わせていますし、医師自身も患者さんが必要とする情報を提供して、患者さんと二人三脚で治療を進めていきたいと考えています。
まずは医師に質問をしてみましょう。また、医師に言いだしにくい場合は、話しかけやすい看護師に「相談」するのも方法の1つです。

どんなことを相談したらいいの?[2]
MSの治療で大切なこととは、何でしょうか?
患者さんは、患者である前に「ひとりの人間」でもあります。病気を少し忘れて楽しむことも大切です。
そのために、医師や看護師に「本当はやりたいと思っていること」や「何を実現したいか」などを「相談」してみることもお勧めします。